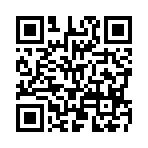2021年10月18日
一回聞いたら覚えてしまう子は何が違うのか?

《暮らしの中で世界地図を身近にする小さな仕掛けも》
一回習っただけで、
特に大きな苦労なしに覚えちゃう子っていますね。
そういう子はなぜ一回で頭に入ってしまうのでしょうか?
たとえば、ある新しい言葉を覚えるのに、30回聞いたりしゃべったりする必要があるとしましょう。
子どものうちはほとんどがそうだと言っても良いくらい、周りの大人が話す言葉だってわからない言葉だらけ。
でも、意味なんてわからない。
わからなくても、子ども達は聞いている。
耳から、音として。
そう、特に聞こうと思って聞いているという状態ではない場合も含めて、
とにかく、耳に入ってる。
そして、なんとなく耳にはなじんでるけれど意味ははっきり知らない、という蓄積をいつの間にか積んでいて、
ある時、それがなんなのかを習うのですね。
その、オフィシャルに習った瞬間がその子にとって30回目なのか、
はたまた聞いたことのない初めての言葉なのか。
実はそういったシンプルな差である事がとても多いんだろうな、と現場で子ども達を見ていて実感するのです。
生まれ持った能力の違いがゼロとは言いませんが、
ほとんどの子ども達の学力の差は、育つ環境の差が作っています。
ここで言う「育つ環境」というのには、
単に親に財力があるかどうか、などという事ではありません。
親を中心とした、その子のまわり大人の関わり方の影響は本当に大きいなと感じるのです。
普段の暮らしの中で、家庭内の話題が幅広かったり、
実際の体験の幅が広かったり、
読書などの世界を通じての擬似体験の量が多かったり、バラエティに富んでたり、
そういう事が1日、1日と積み重なって、5年も10年もとなっていく事で、
いつのまにか、30回目を迎える基礎が頭の中にたっぷりと詰まっている。
そんな子が、一回聞いたら覚えてしまう子、なんですね。
子どもが育つ環境の一番のキーはもちろん親をはじめとした家庭内の大人ですが、
その環境作りの役目に、家族外の立場でできる事をたっぷり持っている大人として、
日々お役に立っている喜びを実感しています。
Posted by みーせん at 08:08│Comments(0)
│教育 〜私達の役目と手法〜