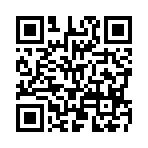2009年05月22日
もじゃもじゃ

ヒゲもじゃおじさんを思い浮かべた時その顔にある毛を、
日本語ではひとまとめに「ヒゲ」と表現してしまえる。
実はこれ、
なんと便利なというか、
怠慢表現というか、
とにかく大胆なまとめ方。
ヒゲもじゃ熊状態を英語ではとてもひとつの単語では表現できない。
鼻の下に生やしているのは "mustache"、
あごに生やしているのは "beard"、
その上下をつないでしまう勢いのは "mustachios"、
その辺りにヒゲのない人が伸ばしてるとヒゲ扱いしてもらえないコウモリみたいな身分のが "sideburns"、
熊おじさん状態の人だとヒゲの一部なのに、
ここしかない場合はなぜか「もみあげ」と呼ばれて、
どちらかというと髪の毛が進出してきたっていう扱い。
そして、ヒゲもじゃの仕上げの上記すべてをまだまだ埋め尽くすのが "whiskers"
ほおの下半分を覆ってしまう存在感のある量と面積を誇る。
これだけの数の単語でしか表現できない事を、
なんと日本語はあっさりとひとこと、
「ヒゲ」だけでひとくくりにしてしまうという、
まったくもって乱暴かつ大胆な話。
この背景には、結構おもしろい理由が隠れているンだけど、
今日の所はここまでにしておきますね。
あ、もひとつ言うなら、あごの先っぽにチョボッとある山羊さんみたいなヒゲが、"goatee"
え?
まんまやって?
あはは。
確かに。
でも、ちょっとだけ語尾に "ee" なんかついちゃって、
かわいい感じというか何というか、
愛嬌を表してるトコロに注目、っていう言葉ですね。
Posted by みーせん at 09:00│Comments(4)
│英語クイズ
この記事へのコメント
赤身、大トロ、中トロ
→tuna
逆バージョン!?
→tuna
逆バージョン!?
Posted by とおりすがらずぅ at 2009年05月22日 10:28
言葉には、その民族がどういうところに重きを置いたり、注目して生活してきたのかが反映されてて面白いですよね。逆バージョンしかり。
そういうものはいっぱいありますね。
違うかもしれないけど、
不規則動詞って、しょっちゅう使うから、語尾edまで聞かなくても瞬時にわかりやすくするためにああなったのかなぁ って、体感として思ったのは、
子供が、言葉を話し始めたころ、できるを「しれれる」って言った瞬間ですね。
そうだよ、あんたが覚え始めた規則に当てはめると、する→しれれる だよなぁ。
でも、ちょっと言いにくいし、聞き取りづらい。
どの段階で「出来る」という言葉が出来たのかはしらないけど、しょっちゅう使うから便利に変化したんだろうさ、と。
英語も日本語も生きている言葉で面白いですねぇ。
話がそれましたが。
日本語だと、こういう表現しかないのに、英語だとこれだけある。
その逆。
それは何故なんだろう。
歴史・文化・地理・etc どんな背景があるんだろう。
これをテーマ子供に話し合いをさせたら、とっても楽しそうですね。
そういうものはいっぱいありますね。
違うかもしれないけど、
不規則動詞って、しょっちゅう使うから、語尾edまで聞かなくても瞬時にわかりやすくするためにああなったのかなぁ って、体感として思ったのは、
子供が、言葉を話し始めたころ、できるを「しれれる」って言った瞬間ですね。
そうだよ、あんたが覚え始めた規則に当てはめると、する→しれれる だよなぁ。
でも、ちょっと言いにくいし、聞き取りづらい。
どの段階で「出来る」という言葉が出来たのかはしらないけど、しょっちゅう使うから便利に変化したんだろうさ、と。
英語も日本語も生きている言葉で面白いですねぇ。
話がそれましたが。
日本語だと、こういう表現しかないのに、英語だとこれだけある。
その逆。
それは何故なんだろう。
歴史・文化・地理・etc どんな背景があるんだろう。
これをテーマ子供に話し合いをさせたら、とっても楽しそうですね。
Posted by ジュンコ at 2009年05月22日 10:51
とおりすがらずぅさん、
おお〜、
それそれ、おもしろいです〜
おお〜、
それそれ、おもしろいです〜
Posted by みーせん at 2009年05月23日 01:15
at 2009年05月23日 01:15
 at 2009年05月23日 01:15
at 2009年05月23日 01:15ジュンコさん、
子供さんの成長を見守る目線がジュンコさんらしくって楽しいなあ〜
言葉の変化はまったくおっしゃる通り。
言葉は生き物なので、出番が多いほど変身していくのですね。
歴史が長い国の言語ほど方言の分化が激しかったのとよく似ています。
方言については、テレビの普及度や人の移動方法の発達と共に分化が鈍り、逆に標準語化に流れましたけれど。
子供さんの成長を見守る目線がジュンコさんらしくって楽しいなあ〜
言葉の変化はまったくおっしゃる通り。
言葉は生き物なので、出番が多いほど変身していくのですね。
歴史が長い国の言語ほど方言の分化が激しかったのとよく似ています。
方言については、テレビの普及度や人の移動方法の発達と共に分化が鈍り、逆に標準語化に流れましたけれど。
Posted by みーせん at 2009年05月23日 01:33
at 2009年05月23日 01:33
 at 2009年05月23日 01:33
at 2009年05月23日 01:33