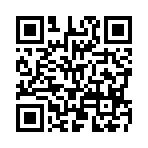2016年11月27日
思春期までは英語を遊びと思うべき8の理由 〜その2〜
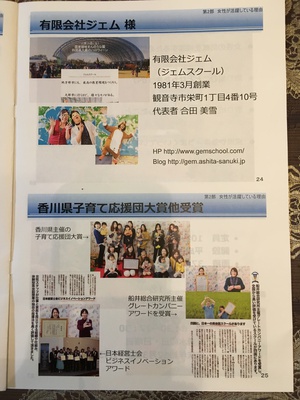
《先日のセミナーでジェムをご紹介下さった資料のページ。ジェムのホームページに数多ある写真からいくつかを選ぶとこういうセレクションになるんか〜ぁ、と興味津々。香川県が開いたセミナーなので、全国規模の受賞(船井総研さん、日本経営士会さん等)よりも「香川県子育て応援団大賞」の方が扱いが大きい》
真に子供のためを考えた英語教育を行うには、
せめて思春期の入口に差し掛かるまでは、
英語を身に付ける事=楽しい遊びの一種
だと感じてもらう事が重要です。
私達がそう考える、その理由を理解するには、
まず、しっかりと区別しておくべき重要な事があります。
それは、
英会話 と 英語 は同じではない
という事。
母国語の習得過程を考えるとわかりやすいので、
みなさん、あかちゃんや子供達が日本語を身に付けていく過程を想像してみて下さい。
そうすると、俗に言う「語学の4技能」の特徴がクリアにわかります。
 聞いて理解する力
聞いて理解する力 耳だけで(目を使わず←ココ重要)理解できる力
耳だけで(目を使わず←ココ重要)理解できる力(赤ちゃんは聞いてわかってるけどまだしゃべれない時期がありますね)
 しゃべって相手と意味を伝え合う力
しゃべって相手と意味を伝え合う力 聞く能力がないとしゃべれない
聞く能力がないとしゃべれない(カタコトでおしゃべりでき始めの頃、まだまだ読むのは先ですね)
 読めて意味がわかる力
読めて意味がわかる力 聞く力(=発音)なしでは読めない
聞く力(=発音)なしでは読めない(文字を認識し、その音を頭の中で再生して理解する必要があります)
 書いて伝える力
書いて伝える力 しゃべる力がないと書けない
しゃべる力がないと書けない(書くというのは頭の中でしゃべっている事を文字にする作業です)
こうやって整理してみると、
言語の能力は、
聞く力 > しゃべる力・読む力 > 書く力
というのが自然な姿なのがわかりますね。
習得の順序も、
聞く力は、一番最初に「身に付く=使えるレベル」になります。
0才の時どころか生まれる前、お母さんのお腹の中にいる後半にはもう会話を聞いていると言われていますね。
しゃべる力は、その次、1才前後からモノになり始めます。
読む力は、文字への興味を持ち始める時期には差があるものの、主には幼児期にたどたどしく読み始める頃がやってきます。
ところが、書く力に至っては、本当の意味で「書く」事がモノになるのは、平均的には小学校できちんとした「勉強としての国語教育」を受け始めてから、まだ更に何ヶ月も経ってからになります。
そこで重要なのあ、生き物としての「ヒト」の仕組み。
驚きの仕組みを、明日はお話しますね。